|
■文字を使った式
【文字式の書き方】
(1)
「文字と数字」,「文字と文字」の間の掛け算の記号×は省略します.
(1’) 「文字と数字」,「文字と文字」の間の足し算,引き算の記号+, −は省略できないので注意
(2)
「文字と数字」の積では数字を前に書きます.
(3)
割り算の記号÷は,分数で表します.
(3’) 分数の「横に掛けてある」ことと「分子にある」ことは同じであることに注意
【例】 a=, x=, 【基本の例】
(1)2×a → 2a,3×x → 3x
(1”) 文字が2つ以上あるときは,アルファベットの順
(2)5×a → 5a,x×6 → 6xa, b, c, ..., x, y, z の順に書くのが普通です(絶対ではないが,特別な事情がなければこの順だと覚えた方がよい). (3)3÷7 → ,x÷3 → …割る方が分母 3x÷7 →
なお,次の下の例のように,すでに掛け算の記号×が省略されているものは,1つの値として扱います.
3÷7×x=x ← xは掛け算(分子)に入る
3÷7x=3÷(7x)= ← xは割り算(分母)に入る
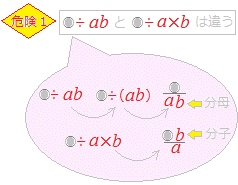 【特別なもの】
(*1)
1aは,単にaと書きます. 1xは,単にxと書きます. ……他の文字でも同様です.
これは世界共通の約束事です.
日本語とよく似ていて,1りんご
(*2)
−1aは,単に−aと書きます. −2aは,−2aと書きます. …他の負の係数でも同様です. −1xは,単に−xと書きます. −2xは,−2xと書きます. ……他の文字でも同様です.
上の(*1)で述べたように,1aがaだから−1aは−a
(*3)
0aは,単に0と書きます. 0xは,単に0と書きます. ……他の文字でも同様です.
※〜何でもない小さな項目に見えますが,間違いやすいところです.〜※
【要約】1a, 0a, a, −aの混乱がかなりあると考えられますので,まず次の表を見てください.
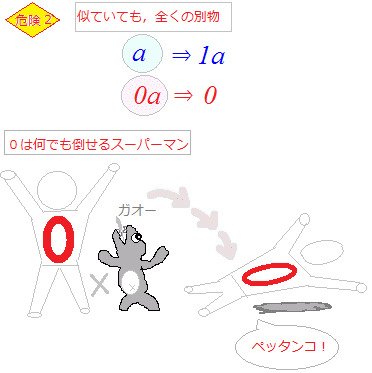 右に続く→↑
|
→続き
(*4)
小学校で使った「帯分数」は,掛け算と間違いやすいので中学校・高校の数学ではなるべく「帯分数は使わない」ようにし,仮分数で表すようにします. 例えば,帯分数と文字の積2aは,実際には(2+)a を表しますが,帯分数の+の記号を省略して1つの数を表します.この事情は文字式での約束とは別の話で,混乱しやすいので「中学校・高校の数学では帯分数はめったに使わない」.  2a → a −1a → −a  (以下は問題) (以下は問題)
【問題1】
文字式の表し方にしたがって,左欄の式を書いたときに右欄の式になるかどうか答えてください.
|
|
※順不同でまとめのチェック
【問題2】
文字式の表し方にしたがって書くとき,左欄の式に等しいものをそれぞれ右欄から選んでください. ○ はじめに左の欄から1つ選択して,続けて右欄から選んでください.やり直すときは,左の欄を選び直してください. ○ 正解の場合は左欄が消えます. |
【問題3】
文字式の表し方にしたがって書くとき,左欄の式に等しいものをそれぞれ右欄から選んでください. ○ はじめに左の欄から1つ選択して,続けて右欄から選んでください.やり直すときは,左の欄を選び直してください. ○ 正解の場合は左欄が消えます. |